2024年3月27日 15 : 00 - 17 : 00
坂井 修一教授 最終講義
講義テーマ
情報今昔物語

(坂井修一教授最終講義 準備委員会より)
東京大学で二十七年にわたり教鞭をとってこられました坂井修一教授が、令和六年三月末日をもって定年退職されます。先生は計算機システムとその応用をご専門に、人々と共存する高性能・高信頼・安全なシステムの研究を推進されてこられました。また、学内においては総長補佐、大学院情報理工学系研究科研究科長、副学長、附属図書館長を歴任され、大学全体の発展にご尽力されてこられました。歌人としても広く知られている先生は、近年では文理融合をめざした活動をされていらっしゃいます。先生の新たな門出に際しまして、以下の通り最終講義を開講させていただきたいと存じております。ご多用な時期と存じますが、是非ご来臨賜れば幸いに存じます。
坂井修一教授最終講義「情報今昔物語」
(アーカイブ動画)
最終講義について
テーマ
「情報今昔物語」
場所/日時
2024年3月27日 15 : 00 - 17:00
参加方法
最終講義はYouTubeにてライブ配信行われます。下記よりご登録ください。
式次第
| 14:30 | 開場 |
| 15:00 - 17:00 | 最終講義 |
| 17:00 - 18:00 | 談話会 |
※予定時間を前後する可能性があります。あらかじめご了承ください。
坂井教授より
最終講義に向けてひと言
坂井 修一教授 ご略歴
情報理工学者
| 1981年 | 東京大学・理学部・情報科学科 卒業 |
| 1986年 | 東京大学・大学院工学系研究科・情報工学専攻 修了。工学博士 |
| 1986年 | 通産省・工業技術院・電子技術総合研究所研究員 |
| 1991年 | より米国マサチューセッツ工科大学 (MIT) visiting scientist |
| 1993年 | 新情報処理開発機構(RWCP)超並列アーキテクチャ研究室 室長 |
| 1996年10月 | 筑波大学・電子・情報工学系 助教授 |
| 1998年4月 | 東京大学・工学系研究科・電気工学専攻 助教授 |
| 2001年4月 | 東京大学・情報理工学系研究科・電子情報学専攻 教授 |
| 2002年10月 | 東京大学・総長補佐 (2004年3月まで) |
| 2013年4月 | 東京大学・情報理工学系研究科・研究科長 (2016年3月まで) |
| 2021年4月 | 東京大学・副学長・附属図書館長 |
著書(単著のみ)
| 2003年 | 論理回路入門(培風館) |
| 2004年 | コンピュータアーキテクチャ(コロナ社) |
| 2009年 | 実践コンピュータアーキテクチャ(コロナ社) |
| 2010年 | 知っておきたい情報社会の安全知識(岩波書店) |
| 2012年 | ITが守る、ITを守る ―天災・人災と情報技術―(NHK出版) |
| 2022年 | サイバー社会の「悪」を考える(東大出版) |
受賞
| 1989年 | 情報処理学会 研究賞 |
| 1990年 | 電総研 業績賞 |
| 1991年 | ・情報処理学会 論文賞 ・日本IBM 科学賞 ・元岡記念賞 |
| 1995年 | ・市村学術賞貢献賞 ・IEEE Outstanding Paper Award (ICCD) |
| 1996年 | 科学技術庁 注目発明 |
| 1997年 | SUN Distinguished Speaker Award |
| 2010年 | 情報処理学会フェロー 認定 |
| 2011年 | 電子情報通信学会フェロー 認定 |
| 2012年 | 大川出版賞 |
| 2018年 | 電子情報通信学会業績賞 |
など
歌人
1978年「かりん」入会と同時に作歌開始
現在、「かりん」編集人。現代歌人協会副理事長。日本文藝家協会理事。
角川短歌賞、塚本邦雄賞、近藤芳美賞、現代短歌大賞 選考委員
歌集(以下、単著のみ)
| 1986年 | ラビュリントスの日々 |
| 1992年 | 群青層 |
| 1996年 | スピリチュアル |
| 1999年 | ジャックの種子 |
| 2002年 | 牧神 |
| 2006年 | アメリカ |
| 2009年 | 望楼の春 |
| 2013年 | 縄文の森、弥生の花 |
| 2014年 | 亀のピカソ |
| 2017年 | 青眼白眼 |
| 2019年 | 古酒騒乱 |
| 2023年 | 塗中騒騒 |
評論集など
| 1996年 | 鑑賞・現代短歌 塚本邦雄 |
| 2006年 | 斎藤茂吉から塚本邦雄へ |
| 2009年 | 界と同じ色の憂愁 |
| 2010年 | ここからはじめる短歌入門 |
| 2021年 | ・森鷗外の百首 ・蘇る短歌 大好きなうた、ちょっと苦手なうた ・世界を読み、歌を詠む |
| 2022年 | うたごころは科学する |
など
受賞
| 1987年 | 現代歌人協会賞 |
| 2000年 | 寺山修司短歌賞 |
| 2006年 | 若山牧水賞 |
| 2007年 | 日本歌人クラブ評論賞 |
| 2010年 | 迢空賞 |
| 2015年 | 小野市詩歌文学賞 |
など
坂井修一教授最終講義 準備委員会
lec_contact@mtl.t.u-tokyo.ac.jp

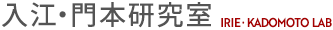
本学工学系研究科で学位をいただき、コンピュータの研究開発をするようになって、38年、東大に赴任してからも27年が経ちました。皆様のおかげで恵まれた職業生活を送ることができました。感謝申し上げます。
いろいろ思うことはあるのですが、最終講義の中で申し上げることとして、ここでは2015年の入学式で披露させていただいた式辞を再掲しておきます。あれから9年が経ち、重ねた思いもありますが、まずはひと言、ということで記しておきたく。
平成27年度東京大学大学院入学式 大学院情報理工学系研究科長式辞
このたび、東京大学大学院に入学ならびに進学された皆さん、本日は本当におめでとうございます。また、皆さんを物心両面で支えてこられたご家族・関係者の方々におかれましても、このよき日をお迎えになったことを心よりお祝い申しあげます。
これから皆さんは、知の専門家として、さらなる一歩を踏み出すことになります。これまで学部や修士課程で得た学術的知識、培ってきた洞察力や新しい思考法などをさらに高度なものとし、やがて独自の知的生産を行っていくことになるわけです。
皆さんは今、希望に燃えているとともに、「はたして自分に何がどこまでできるのだろうか」という不安をかかえているのではないでしょうか。また、「将来希望する職業につけるだろうか」、「指導教員や研究室の人達とうまくやっていけるのだろうか」、「学生生活を長く続けることで家族や恋人に迷惑をかけるのではないか」、といった悩みをお持ちかもしれません。
私自身もそうでした。
私は、大多数の皆さんの2倍以上の年月を、すでに生きております。本学理学部を卒業し、修士課程・博士課程を工学系研究科で過ごし、学位を得てから29年、教育研究を職業として、どうにかやってきました。その私が大学院に入学するときに抱いていた不安や悩みのいくつかは、その後、大きく深くなりこそすれ、解消することはありませんでした。意外に思われるかもしれませんが、それこそが私自身の一番大切なことだったと思うのです。
私自身の専門は、情報システムの構成法とその応用です。と聞くと、皆さんは私のことを、時代の最先端のコンピュータやインターネットをやっているばりばりの理系人と思われるでしょう。職業人としての私は、まさにそういう立場で生きてきました。
一方で、私は、「人間社会は時代とともに進歩するものだ」という考えかたを言葉そのままには受け入れられない、理系では珍しいタイプの人間でもありました。
15000年前のラスコーの洞窟壁画を超えるものを、現代アートの画家達は描いているのか。我々が使う最新のITデバイスは、はたして縄文時代の火焔土器を凌駕するものなのか。精密さや利便性ではイエスであり、そのことの価値は否定しませんが、精神性や芸術性においてはどうなのか。私の場合、そういう疑問が、何をするときでもやみがたく湧き上がってきたのです。
同じことは、1300年前の『万葉集』の詩歌と今の小説、ベートーヴェンと昨今の作曲家など、さまざまな場面で問われうることでしょう。私は、いつもそういう問いを抱きながら、情報理工学の研究を、そして教育をしてきました。
ここで私は、私見にもとづいて、文明批評や文明批判を申し上げたいというわけではありません。そうではなく、もし皆さんが、同様のことや、もっと別のことで悩み、自分のやっていることに疑問を感じておられるとしたら、その悩みや疑問のうちでもっとも重いものは、たぶん一生皆さんをとらえて離さないだろう、ということを、自分の来し方を振り返って申し上げたいのです。
私の場合、コンピュータの研究が一段落するごとに、こうした「悩み」を軸として物事を組み立て直し、次の仕事を考えていくのが、習い性になっております。皆さんぐらいの年齢から10年間ぐらいは、私の研究テーマは、速くて便利なコンピュータを作ることでした。その後、信頼性や安全性が高いコンピュータ、ヒトに優しいコンピュータ、というふうに、テーマをシフトさせてきました。そして今は、ヒトを真に幸せにするコンピュータの研究に取り組もうとしています。そこには、これからの情報理工学が、経済的豊かさだけでなく、精神的・芸術的豊かさにいかに貢献するべきか、という大きな問題が含まれているはずです。
文科系・理科系を問わず、学問というものは、一般に、これに注力し推し進めることで、すぐにゴールにたどりつくというものではありません。むしろ、その過程で課題はだんだん大きなものにふくらみ、われわれの抱える葛藤はより深くなり、時としてわれわれは、より孤独でより苦しい立場に立たされるのではないでしょうか。そしてその孤独や苦しみこそが、学問の醍醐味ではないかと、私は思っています。
さて、皆さんの中には、純粋に学問のことだけを考えて毎日を過ごすことのできる恵まれた方もいらっしゃるかもしれませんが、大部分の方は、日々に生活していくための配慮を、学習や研究の場においてもせざるをえないのではないかと思います。これは、現代の社会システムの中の大学とその構成員の立ち位置を考えれば当然のことです。自分と家族の生活を安定させたい、地位や名誉がほしい、など、大声で言うことではないかもしれませんが、人間として自然な欲求です。
皆さんが実社会においてどのような立場に立っているのか、あるいはこれから立つことになるのかは、たとえばマックス・ウェーバーの『職業としての学問』などを読めば、理解の端緒は得られると思います。
また、ひたすらに勉強し、研究するといっても、世俗的な運不運はつきものです。「人生は芝居のごとし、上手な俳優が貧乏になることもあれば、大根役者が殿様になることもある」という福沢諭吉の言葉もあります。名誉や金銭も大切なものではありますが、これらにこだわりすぎず、俗世間とは不即不離の関係を上手に築き、バランス良くつきあうことが大切かと思います。
ここで、さらによく肝に銘じておかなければならないことがあります。人間はもともと肉体的に弱い生き物ですが、精神的にもとても脆いものだということです。いろいろな事柄についてこれを自覚する必要がありますが、なかでも研究倫理の問題は、繰り返し自戒しなければなりません。剽窃するな、捏造するな、ということは言を俟ちません。こうした規範とともに、規範を破っても楽をして名誉や地位を手に入れたいという間違った考えに陥らないよう、よくよく注意していただきたいと思います。
「初心忘るるべからず」とは室町時代の能楽師世阿弥の言葉です。使い古された言葉ではありますが、皆さんは、本日ここに出席されている気持ちを、「初心」として忘れないようにしてください。倫理にもとる行動は、初心を生き生きと再現できる精神からは決して起こらないものです。いくつになっても初心を忘れない人こそ、真に優れた人であると、私も心から思います。
皆さんは、私などの知らない新しい世界を築く人達です。その皆さんの前には、人類社会のたくさんの深刻な問題 ― 人口爆発と食料やエネルギーの枯渇、先進国の高齢化、地球温暖化と環境破壊、地域間そして世代間の経済格差など ― が待ったなしで押し寄せてきています。
皆さんの中には、あるいは、自分は純粋科学の徒であって、こうした社会的課題を現実に解決する人間ではないとお考えの方がいらっしゃるでしょう。たしかに、自然知・人文知の原理を探求する立場からは、世俗的な課題解決は遠いことがらかもしれません。
しかし、世の中にはじっさいに個々の現場で解決する役割もあれば、人類社会のための思想的基盤を構築したり、理学的な真実をつかまえたりすることで解決への糸口を提供する役割もあります。次の時代に、学問と社会の間でどういう因果応報が起こるかは、誰にもわからないことです。両者の関係について日頃から頭に入れておき、新しい時代を築くための想像の翼をいつも広げておくことが、どんな立場の人にもたいせつと思われます。
最後に一言だけ。「学問に王道無し」と言いますが、楽をしたり近道したりすることで、かえって本物を手に入れられなくなるものだということは、人生そのものについても当てはまります。ほんとうにたいせつなことは、苦しみや悲しみを深く経験してはじめて味わえるものだ、といっても良いでしょう。
たとえばレンブラント晩年の自画像に描かれた彼自身の顔は、美醜が複雑に入り交じった表情をしていますが、こうした高度な芸術は、苦しみ悲しみを自分のものとしてきた人でないと味わえないものでしょう。ジャズの名曲「ラッシュ・ライフ」は我々の欲望がもたらす人生の機微を語ってくれますが、これを理解するには、やはり人間らしい喜怒哀楽の経験が必要です。絵画だけでなく、音楽だけでなく、家族や友人とのささやかな語らいの場でも、苦労の末にこそ深い幸福感は味わえるものです。単純な世俗的成功よりも、むしろそうした彫りの深さをもつことのほうに、私などはより大きな価値を置きたいと思いますし、こうした思いは、年齢を重ねるとますますはっきりとしてきます。
まだまだ語り尽くせないのですが、もう時間になりました。これからの皆さんのご健康とご健闘を心から祈ることで、私の式辞を終わりにしたいと思います。皆さん、深い悩みを抱えることがあっても、広い心で悠々とこれからの学究生活を楽しみ、さらに人生そのものを生き抜き、そして自分らしい彫りの深い幸福を手にしてください。
平成27年(2015年)4月13日
東京大学大学院情報理工学系研究科長 坂井 修一